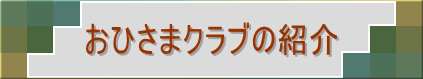 |
自閉症児の親の会がNPOへ。「圧倒的少数派」から、一般の人も参加する会にしたい。 |
『おひさまクラブ』は1998年1月に、大平町に在住する発達に遅れのある子を持つ3 名の母親によって発足しました。当初の活動目標は普通学級に在籍する軽度の発達障害を もつ子の通級指導教室を大平町につくることでした。当時、栃木市にある栃木第二小の 「ことばの教室」が受け入れ先になっていましたが、待機児童の数が多くなり、何年も待 たないと入級できないという状況でした。そこでそのような状況を改善すべく、母親たち が動き出しました。大平町の対応も早く、わずか1年で大平中央小に「ことばの教室」 (通級指導教室)ができました。その後『おひさまクラブ』は、発達に遅れのある子ども を持つ母親の交流の場として、活動を維持していくことになりました。 |
しかし、母親は家事・育児・子ども達の行事などで大変に忙しく、またその上親の会の運 営ともなると、その負担は相当のものになります。もともと親の会は、何かの要望を通す ために結成されることが多く、基本的に活動も短期決戦型になりがちです。『おひさまク ラブ』も当初の活動目標を果たすと、自然に活動が鈍くなりましたが、そこへ母親たちの 活動に触発された父親たちが徐々に活動に参加し始め、「子どもたちの将来のために、何 かを残しておきたい」「10年後、20年後の先を見据えて今から準備していこう」と思 った父親たちが集まり、2001年4月、父親が中心となり運営する新しい『おひさまク ラブ』になりました。そして、活動を継続していくために「NPO法人」を申請し、12月認 証。自閉症と周辺児者へのサポートグループ『NPO法人おひさまクラブ』となり、今日に 至っております。 |
2001年度は、日本財団からの助成金で、自閉症と周辺の障害についての理解を深めて もらうための講演会事業を中心として、月1回の定例会、親子親睦会、行政への提言活動 を行いました。年6回行った講演会には、のべ1293人の参加がありました。この講演 会のビデオを県内の情緒障害学級50学級及び知的障害養護学校8校、未就学児通園施設 12施設等、県内80カ所に無料配布いたしました。 |
2002年度は筑波大学心身障害学系と連携を取り、社会福祉・医療事業団子育て支援基 金から助成をいただき、療育訓練プログラムを立ち上げました。(2003年度からおひ さまサポートプログラムと名称変更)。現在17人の子ども達が個別指導を月1回受けて おります。療育に関しては、親が家庭で行うことを前提として、いろいろなことを教える やり方を、療育担当者から1時間のセッションの中で教わるという形式を取っておりま す。また、8月に「自閉症児者とその家族への適切な療育指導の実施体制の整備に関する 要望書」を栃木県知事宛に提出しました。その後10月に県が「自閉症・発達障害支援セ ンター」設置へという具体的な行動につながりました。 |
私たちが常々感じていることですが、障害を持つ子どもたちが同一の機関や専門家と、幼 児期から成人期まで一貫して関わっていくということは、極めて少ないと思います。各ラ イフステージでそれぞれの機関に相談に行き、初めて会う担当者と話をして、子どものこ とを理解してもらいながら、必要なサービスを受けることになっています。親としてはい つまでも将来のことに不安を抱えながら、子どもとともに暮らしていかなければなりませ ん。それぞれの問題にそれぞれの専門家がバラバラに対応するのではなく、子どもの生活 全体を視野に入れて、一貫した関わりを持つことができれば、親や子どもの混乱はもっと 少なくなるはずです。 |
それから障害者の自立と社会参加が叫ばれて久しいですが、大切なのは地域で障害者が生 きていくことができるシステムづくりではないでしょうか?将来自立して地域で生きてい くのに、必要なスキルを獲得するための療育を幼児期から行っていない状況で、言葉だけ のノーマライゼーションは理念のみが先走り、非常に問題だと思っております。特に知的 障害や自閉症の場合、今の体制では無理だと思います。『おひさまクラブ』では、自閉症 のみならず障害児者に対しての支援は、ある期間のみではなく一生涯続くと考えていま す。障害児者へのサポートは、1つの機関だけでは対応しきれないので、さまざまな機関 や職種が協力、協同していかなくてはなりません。また、サービスを提供していくにも、 1つの部門に限られたものではなく、複数の機関を超えてしなければならないこともあり ます。現在の形骸化している各機関の連携では諸問題の抜本的解決は難しいと考えており ます。そこで、早期発見から就労、社会的自立に至までの障害児者のデータを一元的に管 理し、各機関(医療・療育・教育・行政・労働・福祉)への指導・管理・評価・研究・ケ ア及び情報交換を、行うことができる上部機関の設置及びそれらのことをコーディネイト できる本物の専門家の集団が必要となります。実現にはかなりの時間を要することになる でしょうが、アメリカノースカロライナ州で行われているTEACCHプログラム(自閉 症及び関連するコミュニケーション障害の子どもたちのための治療と教育)のTEACC Hセンターをモデルとして考えていますので、決して無理な話ではないと思います。 |
私たちの思いは「我が子のみならず、多くの子どもたちに幸せを!」をスローガンとして 掲げ、後から来る子どもたちとその家族に私たちと同じような悩み苦しみを味わってほし くないと思っています。そのためには、障害の違いや年齢別にニーズが変わることなど で、目先の問題のみを取り上げる団体にはならないように心がけ、将来を見据えた継続性 のある活動をしていきたいと思っております。今までの親の会というと、例えば作業所を 作るための親の会や、ある要望を通すために団体として結成された親の会が大半でした。 ですから、障害児者福祉に対する要望も、地域や学校の狭い区域に限定されたものが多 く、一部の活動している親の子どものみが恩恵を受け、それが全体に波及しないことも多 かったと思います。私たちがNPO法人を取得したことも、排他・閉鎖的になりがちの親 の会からの脱却をねらったものであり、多くの一般の方々や地域の方々に信頼される団体 をめざしたものであります。 |
今後は、さまざまな地域で活動されている親の会とも連携を取り、より大きな声として行 政や地域へ訴えていきたいと思っております。私たちは、基本的には圧倒的少数派です。 ですから、各団体がそれぞれに声をあげても、なかなか通りづらいのが現状だと思います ので、やはり連携を取り、お互い情報交換をしながら共に歩んでいこうという姿勢が必要 だと思っております。私たちは「親亡き後どうするのか」という問題で、それぞれの共通 理解は可能ではないかと思います。 最後に私たちの願いは、私たちの子どもが人としての人権が尊重され、偏見や差別のない 社会環境で、子ども達が自ら生活の主人公となって生きていくことです。受け身的に保護 されるだけの存在ではなく、社会の中で彼らなりの「生きる力」を発揮して、自己実現を はかっていくことができる存在であると信じ、育てていきたいと思います。 |